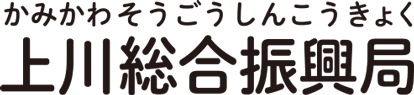上川の農業

はじまり
上川管内の開拓は、寛政10年(1798年)に3人の幕吏が石狩川上流の探検を始め、その後屯田兵村の設定は、明治18年8月屯田兵本部長永山武四郎一行が、近文山で国見をしたのに始まるとされています。
明治23年旭川、神居、永山の三村が設置、以降毎年屯田兵の移住が行われ、同30年11月北海道庁官制が施行されるに伴い、旭川村に上川支庁が設置されました。
平成22年4月、支庁制度改革により上川支庁を廃止し、上川総合振興局を設置しました。これと同時に空知支庁管内から幌加内町が編入され、23市町村を管轄することとなりました
農業は、明治19年に忠別農作試験場が設けられ、豆類、野菜などの作物を試作したことに始まりました。水稲については、同24年6畝歩の水田が初めて試作され、その後10年余り試作時代が続きましたが、同35年北海道土功組合法の制定により水田開発が一気に進みました。
本編
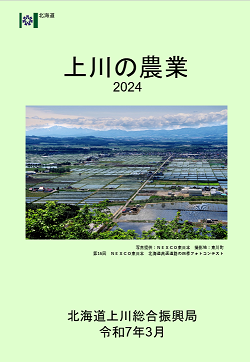
令和7年(2025年)3月28日更新